【2023年日本向け説明会のお知らせ】北京大学大学院燕京学堂(2023/9/9(土)21:00-22:00)
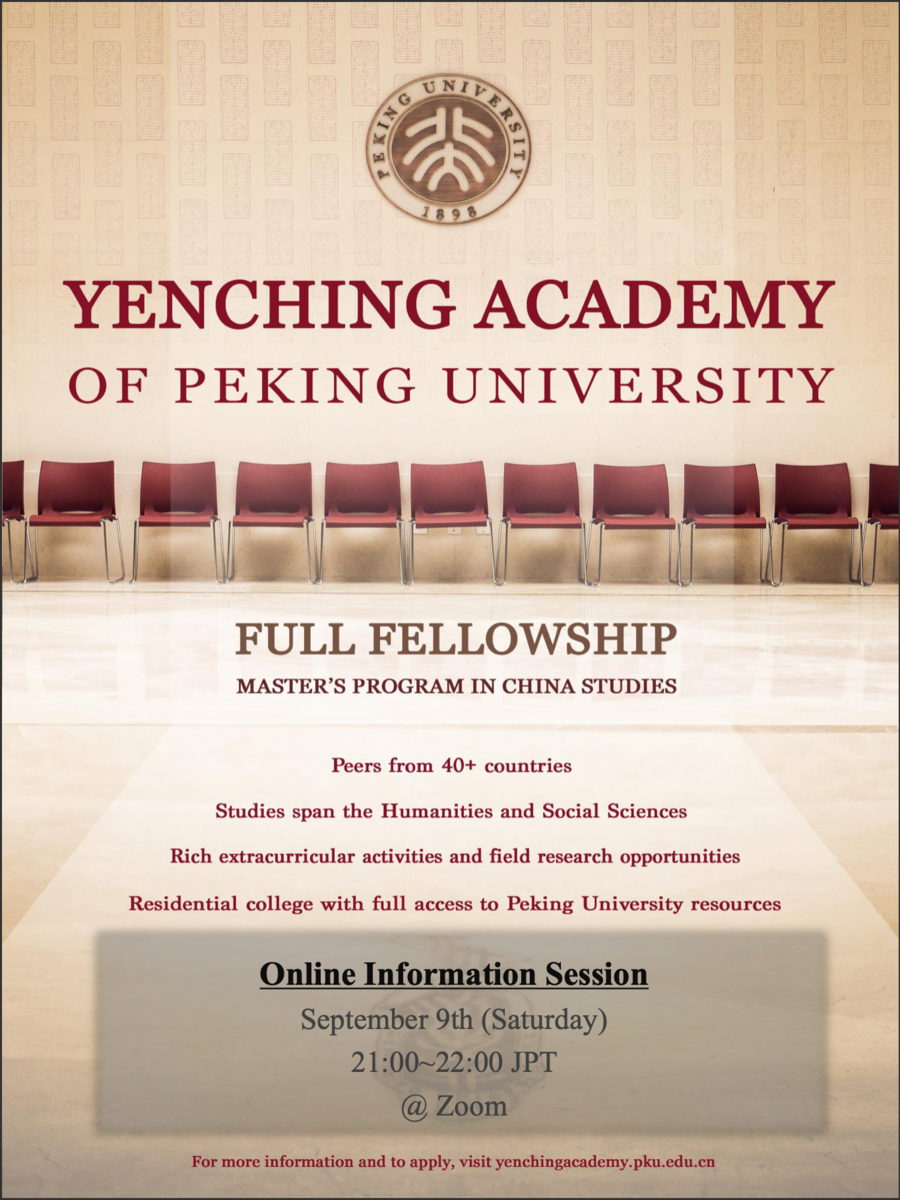

【大学院説明会のお知らせ】
9/9(土)21:00〜オンラインで、中国の大学院に進学したい方やグローバルに活躍したい方、中国に関心のある方を対象に、北京大学大学院燕京学堂(Yenching Academy of Peking University)の説明会を行います!
(説明会は1時間半を予定しています。前半(30分)では、Yenching Academyに関する全般的な説明を行います。後半(60分)では、パネルディスカッションとQ&Aセッションを行います。上の画像では22:00までとなってしまっていますが、実際は1時間半の予定です。)
北京大学燕京学堂は、中国と世界への理解を深めた次世代のグローバルリーダーを養成するために設立された全額支給奨学金修士プログラムです。
奨学生は6つの領域(1.政治学/国際関係学 2.哲学/宗教学 3.文学/文化学 4.法律学/社会学 5.歴史学/考古学 6.経済学/経営学)から専攻を1つ選び、原則2年間で中国学(China Studies)の修士号を修めます。
毎年125人程ある入学枠は、中国を含む約40カ国からの学生で構成されています。
本プログラムの学生は、全額支給奨学金として学費や往復航空券、学生寮、生活費などの支援を受けられることに加え、フィールドトリップなどの豊富な課外活動にも参加することができます!
本説明会は、二部構成です。前半は、日本人奨学生・卒業生(7名参加予定)がプログラムについて説明し、後半では参加者の様々な疑問に直接答えます。説明会での使用言語は日本語(+英語)です。
応募を考えている方はもちろん、関心のある方は是非出席してみてください。
後ほどzoomのリンクを送らせていただくため、Googleフォームからの事前の申し込み必須です!
お待ちしております!
Googleフォーム : https://forms.gle/FfXDXxzM21h8Ldmh8
北京大学燕京学堂のホームページ: https://yenchingacademy.pku.edu.cn
北京大学燕京学堂に関するその他の記事(これらの記事には少し古い情報も含まれるので、最新の情報についてはプログラムの公式ホームページ(上述)もご覧ください):
【2022年説明会のお知らせ】北京大学大学院燕京学堂(2022/10/8(土)21:00-22:00)
【北京大学大学院燕京学堂 日本向け説明会のお知らせ(2023/9/9(土)21:00-22:00)】
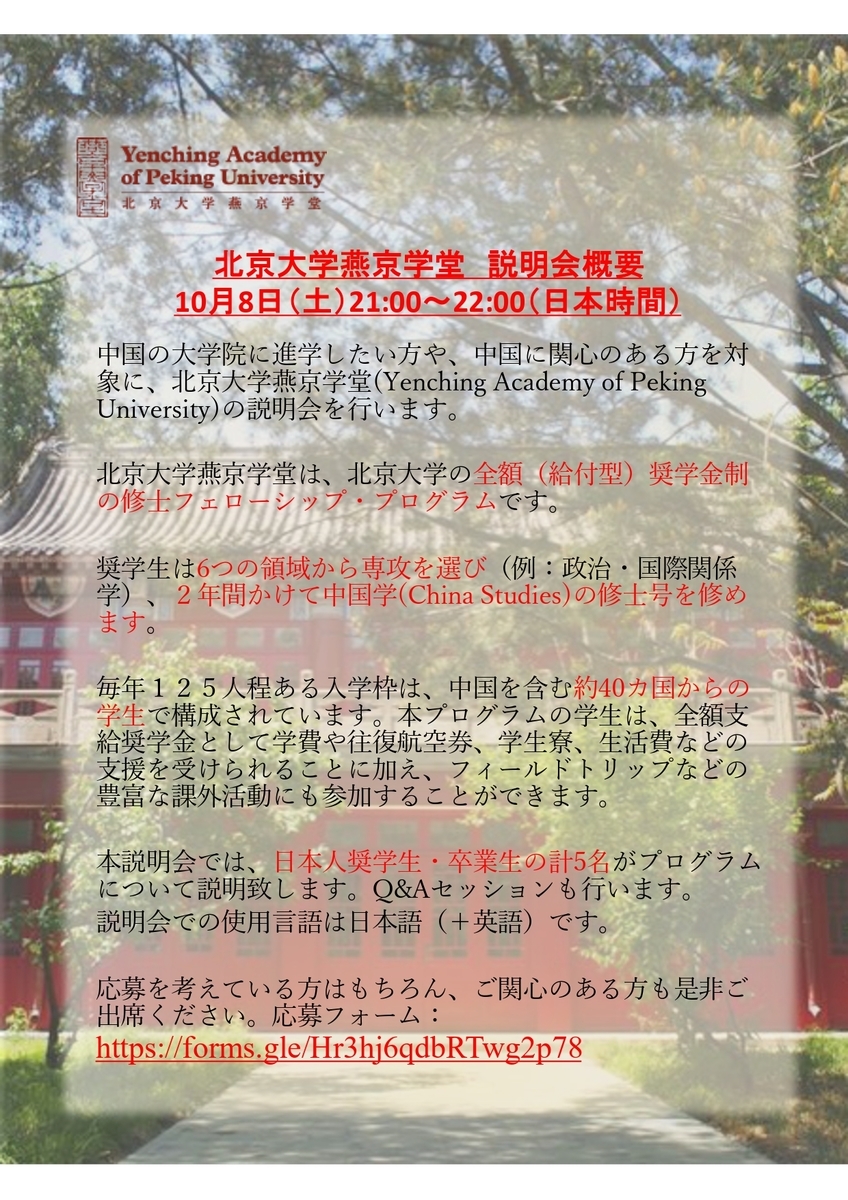
【大学院説明会のお知らせ】
10/8(土)21:00〜22:00にオンラインで、中国の大学院に進学したい方やグローバルに活躍したい方、中国に関心のある方を対象に、北京大学大学院燕京学堂(Yenching Academy of Peking University)の説明会を行います!
北京大学燕京学堂は、中国と世界への理解を深めた次世代のグローバルリーダーを養成するために設立された全額支給奨学金修士プログラムです。
奨学生は6つの領域(1.政治学/国際関係学 2.哲学/宗教学 3.文学/文化学 4.法律学/社会学 5.歴史学/考古学 6.経済学/経営学)から専攻を1つ選び、原則2年間で中国学(China Studies)の修士号を修めます。
毎年125人程ある入学枠は、中国を含む約40カ国からの学生で構成されています。
本プログラムの学生は、全額支給奨学金として学費や往復航空券、学生寮、生活費などの支援を受けられることに加え、フィールドトリップなどの豊富な課外活動にも参加することができます!
本説明会は、二部構成です。前半は、日本人奨学生・卒業生(5名参加予定)がプログラムについて説明し、後半では参加者の様々な疑問に直接答えます。説明会での使用言語は日本語(+英語)です。
応募を考えている方はもちろん、関心のある方は是非出席してみてください。
後ほどzoomのリンクを送らせていただくため、Googleフォームからの事前の申し込み必須です!
お待ちしております!
Googleフォーム : https://forms.gle/Hr3hj6qdbRTwg2p78
北京大学燕京学堂のホームページ: https://yenchingacademy.pku.edu.cn
北京大学燕京学堂に関するその他の記事:
【2021年説明会のお知らせ】北京大学大学院燕京学堂(2021/11/1(月)20:00-21:00)
更新!【北京大学大学院燕京学堂 日本向け説明会のお知らせ(2023/9/9(土)21:00-22:00)】


【大学院説明会のお知らせ】
2021年11月1日(月)20:00〜21:00にオンラインで、中国の大学院に進学したい方やグローバルに活躍したい方、中国に関心のある方を対象に、北京大学大学院燕京学堂(Yenching Academy of Peking University)の説明会を行います!
北京大学燕京学堂は、中国と世界への理解を深めた次世代のグローバルリーダーを養成するために設立された全額支給奨学金修士プログラムです。
奨学生は6つの領域(1.政治学/国際関係学2.哲学/宗教学3.文学/文化学4.法律学/社会学5.歴史学/考古学6.経済学/経営学)から専攻を1つ選び、原則2年間で中国学(China Studies)の修士号を修めます。
毎年125人程ある入学枠は、中国を含む約40カ国からの学生で構成されています。
本プログラムの学生は、全額支給奨学金として学費や往復航空券、学生寮、生活費などの支援を受けられることに加え、フィールドトリップなどの豊富な課外活動にも参加することができます!
本説明会は、二部構成です。前半は、現役日本人奨学生(3名参加予定)がプログラムについて説明し、後半では参加者の様々な疑問に直接答えます。説明会での使用言語は日本語(+英語)です。
応募を考えている方はもちろん、関心のある方は是非出席してみてください。
後ほどzoomのリンクを送らせていただくため、Googleフォームからの事前の申し込み必須です!
お待ちしております!
Googleフォーム: https://forms.gle/358S5Jw34wDuhwpG7
北京大学燕京学堂のホームページ: https://yenchingacademy.pku.edu.cn
北京大学燕京学堂に関するその他の記事:
【2020年説明会のお知らせ】北京大学大学院燕京学堂(2020/11/27(金)20:00-21:00)
更新!【北京大学大学院燕京学堂 日本向け説明会のお知らせ(2023/9/9(土)21:00-22:00)】


【北京大学大学院燕京学堂 説明会のお知らせ(2020/11/27(金)の20:00-21:00)】
2020/11/27(金)20:00-21:00、中国の大学院に進学したい方やグローバルに活躍したい方、中国に関心のある方を対象に、北京大学大学院燕京学堂(Yenching Academy of Peking University)のオンライン説明会を行います!
北京大学燕京学堂は、中国と世界への理解を深めた次世代のグローバルリーダーを養成するために設立された全額支給奨学金修士プログラムです。奨学生は6つの領域(1.政治学/国際関係学2.哲学/宗教学3.文学/文化学4.法律学/社会学5.歴史学/考古学6.経済学/経営学)から専攻を選び、1年半から2年間で中国学(China Studies)の修士号を修めます。毎年125人程ある入学枠は、中国を含む約40カ国からの学生(ハーバード、スタンフォード、オックスブリッジなど各国の著名な大学)で構成されています。本プログラムの学生は、全額支給奨学金として学費や往復航空券、学生寮、生活費などの支援を受けられることに加え、フィールドトリップなどの豊富な課外活動にも参加することができます!
本説明会は、二部構成です。前半は、現役日本人奨学生(3名参加予定)がプログラムについて説明し、後半では参加者の様々な疑問に直接答えます。説明会での使用言語は日本語(+英語)です。
応募を考えている方はもちろん、関心のある方は是非出席してみてください。後ほどzoomのリンクを送らせていただくため、Googleフォームからの事前の申し込み必須です!
お待ちしております!
Googleフォーム:
北京大学燕京学堂のホームページ:
https://yenchingacademy.pku.edu.cn
Yenching Academy合格者インタビュー:眞船弘暉さん 〜弘暉さんや選考について〜

【北京大学大学院燕京学堂 日本向け説明会のお知らせ(2023/9/9(土)21:00-22:00)】
(記事のはじまり)
中国の北京大学大学院にあるYenching Academy(イェンチンアカデミー)。中国と世界への理解を深めた次世代のグローバルリーダーの育成を目的として設立された全額奨学金修士プログラムで、毎年世界中からすごく優秀な学生を北京に集めています。
今回そんなプログラムに、日本人の眞舩弘暉さんが合格しました!おめでとう!
弘暉さんは2020年9月からYenching Scholarとして北京に留学し、1年半〜2年間でChina Studiesの修士号を取ることになります。
そこで、この記事では弘暉さんのバックグラウンドやYenching Academyの選考などについてインタビューしていきます。まだまだYenching Academyに関する日本語情報が少ない中、これから応募を考えている方々の参考になれば幸いです。
ちなみに、私もYenching Academy出身で、本当にすばらしくておすすめしたいプログラムだったので、この記事を書いています。まだまだ日本人は少ないので、もっと多くの日本人に挑戦してほしいです!
ちなみに、Yenching Academyの”ライバルプログラム”とされる清華大学大学院Schwarzman Scholars(シュワルツマンスカラーズ)もすばらしいです!
<インタビュー内容>
- 経歴
- 志望理由
- 興味分野/取り組みたいこと/目標
- 選考スケジュール
- Personal Statementについて
- 推薦状について
- 面接について
- 応募したい人へのアドバイス
------------------------------------------------
(以下、青字:Kazuki、黒字:弘暉さん)
1. Kazuki:まず、弘暉さんの経歴を教えてください。
1. 弘暉:自分は慶應義塾大学商学部の卒業生で、主に国際租税を専攻していました。大学以前は海外に行ったことはほとんどありませんでしたが、学部1年時にケンブリッジ大学のサマースクールに1ヶ月、3年時から4年時にかけてはスペインへ1年間交換留学に行きました。そのため、今ではスペイン語と英語が話せます。ただ、大学以前の海外経験としては、高校時代にサッカーでブラジル遠征に1ヶ月弱行ったぐらいでした。
学外の活動としては、準体育会のサッカー部に所属していました。また、インターンは、投資銀行・VC(ベンチャーキャピタル)業界での経験があります。


Yenching Academy出身の私から見ると、弘暉さんの経歴は、ある意味すごくYenchingぽくないと感じます(笑)。まず、中国経験が全然ない!もちろん、中国経験がない人も全然いるしそれでも全然合格できますが、Yenching Academyに来る外国人学生は何かしらの中国経験のある人が比較的多いです。
また、Yenching Academyの歴代の日本人を見ても(といっても少ないですが...)、メインの興味分野がスタートアップやVCだった人はたぶん初めてです。私もそうですが、Yenching Academyに限らず中国で学ぶ日本人は国際関係や政治に興味のある人が多い気がします。
スタートアップやVCに興味のある日本人は、たいていアメリカなど欧米に行ってしまうと思うので、このタイミングで中国にそれらを学びに来るのはおもしろくていいと思います。実際、私はたいして詳しくないですが、中国のスタートアップとかってすごく勢いのある感じですよね(ユニコーン企業がめっちゃあるし、”中国のシリコンバレー”(深センと北京)もおもしろい)。
あとは、慶應義塾大学からYenching Academyに合格したのは弘暉さんが初めてです!私の母校である早稲田から中国留学に行く人はとても多いですが、慶應からは少ない印象があるので、そういう意味でもとてもいいと思います。
2. Kazuki:次に、弘暉さんがYenching Academyに行きたいと思った理由について教えてください。
2. 弘暉:スペインでの交換留学を通して、多くの留学生とそれぞれの国のスタートアップの現状に関してディスカッションする機会がありました。それまではアメリカにしか目を向けていなかったのですが、そこで気づいたのはスタートアップエコシステムが中国では急速に発展していることです。ただ、その一方で他の多くの国ではまだエコシステムは発展途上であることを知りました。
そのため、実際に中国現地でどのようにエコシステムが発展していったのかを多角的に(スタートアップ・V C・政府のサイドから)学び、将来的にはアジア・中南米にそれらをアプライすることを通して再現性のあるスタートアップのエコシステムの構築、ひいては経済発展に貢献したいと思っているからです。

中国のスタートアップエコシステムについて多角的に学ぶためには、やはり中国現地に行くのが良さそうですね。確かに、欧米のトップ大学などで学ぶこともできますが、それは大部分が座学に限られてしまうのに対して、中国に行けば授業以外にも関係組織訪問や関係者との交流、普段の生活など様々なことからより深く学べるからです(というか、ただ授業で学ぶだけなら本を読み漁ったり、オンラインで受けられる講義などでもいいですよね)。
また、Yenching AcademyにはスタートアップやVC、政府サイドに関わりを持っている人も色々いるし(それらでインターンなどをしている人は多かったし、起業している人もいました)、なによりも、北京大学の目の前には中国のシリコンバレーの一角である"中関村"があるので、そういう意味でもYenching Academy/北京大学はとても良い環境だと思います。
実際、国際関係と政治学を専攻していた僕でさえも、授業内外でスタートアップやVCなど様々なおもしろそうな組織を訪問したり、話を聞いたことがありました。数日間だけですが、あのTikTokを運営しているBytedanceの仕事を手伝ったこともありました。
3. Kazuki:そんな弘暉さんですが、そもそも特にどのようなことに興味があって、どのような目標を持っていますか?Yenching Academyの先にどんなことに貢献したり、取り組んでいきたいと思っていますか?
3. 弘暉:私が特に興味のあることは各国のスタートアップエコシステムです。
将来的には、アジア、中南米のスタートアップエコシステムへ資金提供をするVCになり、多くの起業家の夢をサポートできるようになりたいと思っています。そのために、Yenching Academyでの2年間を通して中国のエコシステムがどうやって急速に発展していっているのかを学んでいく予定です。
具体的には、一年目にはアリババ大学でもアントレナーシップを教えている教授の中国でのスタートアップに関しての授業や、スタンフォードMBAの教授の中国の金融システムのクラスなどを通して、学問的にスタートアップエコシステムを学んでいく予定です。そして、2年目は北京、上海、深センなどでスタートアップやV Cでのインターンをし、実際にエコシステムの中に入っていくことで実践的に学んでいく予定です。
やっぱりスタートアップエコシステムなんですね(笑)。しかも、Yenching Academyの2年間のプランがしっかりと見えていますね(すばらしい!笑)。アリババ大学関連の教授のことは私は知りませんでしたが、確かにYenching Academyにはスタンフォード大学MBAとコラボのような授業があって(中国とアメリカをテレビ電話でつないで授業をする)、それはとてもおもしろいと評判でした。
修士論文を書く以外何をしてもいい(でもビザがあって、好きなことをするのに十分な奨学金をもらえる)という2年目に、北京、上海、深センなど中国のスタートアップやVCが集まっている各地でインターンなどをし、現場から学びを深めるというのはすばらしいですね。自分の興味分野やしたいことに従って非常に柔軟に2年目のプランを決められるのはYenching Academyの特に最高なポイントの一つです。
ちなみに、僕が2年目のときは、中国を訪れる日本人を増やすために、中国全ての省と全ての世界遺産を旅しながら色々な情報発信をしていました(中国制覇はコロナのせいで中断されてしまいましたが...)。だから、2年目はほぼずっと各地を走り回ってホテル/ホステル暮らしをしていたので、北京には全然いませんでした。
(参考:「ミドルキングダムの冒険」:https://middle-kingdom.com )
4. Kazuki:次に、Yenching Academyの応募書類や面接について聞いていきます。
まず、応募から合格までの大体のスケジュールを教えてください。
4. 弘暉:全体として、今年はCOVID-19の影響で「面接の連絡」以降のスケジュールが少し後ろにズレたようです。それを念頭においた上で参考程度に共有すると、今年のスケジュールは以下のような感じでした。
- 自分が「出願」したのは締め切り当日(12月の第一週)
- Yenching Academyから「書類審査合格(面接の連絡)」があったのは2月の最終週
- Skypeで「面接」を受けたのは3月の第一週
- Yenching Academyから「最終合格通知」が届いたのは4月の第一週
5. Kazuki:応募書類(Personal Statement)はどのように準備していましたか?
5. 弘暉:書き方としては、( 理想) - { ( 思い) * (経験) * (スキル) } = ( 学びたいこと)というところを意識し、いかに説得力を増すことができるのかを考えました(この式はTwitterで偶然見かけました。)。具体的には、自分は(理想)=(目標)を持っていて、それのために今までこんな(思い)で、こんなことをしてきて=(経験)、そして(スキル)を持っているが、現状では(理想)との差分があり、その差分を埋めるためにYenching Academyが必要=(学びたいこと)という感じです。
準備に関しては、これまでPersonal Statementを書いたことがある人に読んでもらい、コメントをもらい、そのいただいたコメントを踏まえてあるべきPersonal Statement像に近づけていきました。自分で書いていると煮詰まったり、これでいいと思ったりしますが、そういう時は進んで他の人にコメントを貰うことで異なった視点から見ることができ、より客観的に良いPersonal Statementを最終的に作成することができると思います。
さりげない違いですが、弘暉さんが「Yenching Academyが必要」と表現しているのは非常に非常に重要です。多くの人は、「なぜ自分がそこに行きたいのか(Why I want to attend the Yenching Academy)」ということを応募書類で伝えようとしますが、強い応募書類をつくり、本当に合格するためにはそれでは不十分です。なぜなら、他の応募者もみんな「Yenchingに行きたいっ」と書いているからです。
応募をしているからには、そこに行きたいのは言うまでもなく当然のことです。選考する側からしたら、ある意味そんなことはどうでもいいです。じゃあ、何が合格者と不合格者を分けるのかと言うと、一つは志望動機の伝え方にあると思います。
そして、それが「必要(need)とほしい(want)の違い」だと思います。「自分が成し遂げたいある目標のためにはYenching Academyが必要だ」、そんな風に表現できたり(もちろん無理矢理ではなく理路整然と)、選考者にそう信じさせることができれば、それは他の何百何千の応募者の中から自分を差別化させてくれます。そして、自分を差別化できれば選考を通る可能性も高くなります。
これは、Yenching Academyの応募に限らず、とても大事なポイントです。
6. Kazuki:推薦状はどのような人にもらいましたか?
6. 弘暉:Yenching Academyでは推薦状が2通必要です。重視しているのはリーダーシップ経験だと考えたので、自分のパーソナリティをよく知っているゼミの教授に1通お願いしました。
もう1通は、2年次に履修していた授業の教授(アメリカでPh.Dまで取っており、学生の留学に寛容であると思ったため)にお願いしました。
7. Kazuki:Yenching Academyの面接はSkypeで行われますが、どんな感じでしたか?また、どのようなことを注意したり、どのように準備をしたりしましたか?
7. 弘暉:面接に呼ばれてから実際の面接までの期間は1週間弱でした。
内容に関しては、人それぞれだと思いますが、自分の場合はどうして自分のPersonal Statementに書いた目標を達成したいのかの理由、そしてなぜYenching Academyがそれに必要なのか・Yenching Academyでないといけないのかを深く聞かれた印象です。
一点、自分が面接の時に意識したことは、他の候補者が誰か・どんな人か分からないが簡単に分類し、自分のその中での立ち位置を踏まえ、どうしてYenching Academyは自分を取るべきなのかを考えた事です。具体的には、自分の場合は中国への経験(留学をしていたり、住んだ経験がない)がありませんが、どうやってその経験がある人と差別化し、Yenching Academyに自分を選びたいと思ってもらえるのかを考えました。
基本的な準備に関しては、英語での面接に慣れるためにはオンライン英会話を行い、また内容の深掘りのためには、Personal Statementに関してなにを聞かれてもいいようにipadのロック画面に登録し、毎日自分で読んでいました。
「どうしてYenching Academyは自分を取るべきなのかを考えた」という点もとても大事です。多くの人は自分のことばかり話してしまいますが(志望動機や自分へのメリットなど)、一方で、「自分はプログラムにどんな貢献ができるのか、どんな価値を提供できるのか」もしっかりと分析し、明確に伝えることができると選考する側が受ける印象は全然違います。
8. Kazuki:最後に、これから応募しようと思う人たちへ何かアドバイスをお願いします。
8. 弘暉:まだ何も成し遂げていない自分がアドバイスなどというのは厚かましいですが、一つあるとすれば、その瞬間の自分の手札をしっかりと見極め、面接官の観点からどうやったら魅力的に見えるのかを客観的に理解しようと努めることではないでしょうか。
例えば、自分の場合は中国に行った経験という手札は持っていなく、Yenching Academyに受かるためには一見すると不利のように見えます。その際に、本当にそれは不利なのか?もしかすると、逆に自分を有利な立場に立たせてくれるカードになるのではないかという仮説を立て、実際に面接の最後の一言でそれを言いました。結果としては何が合格をいただいた要因なのかはわかりませんが、自分の中ではそれが一因ではないかと考えています。
来年皆さんと北京でお会いできるのを楽しみにしております。
------------------------------------------------
今回、弘暉さんの協力のおかげで、初めてYenching Academy日本人合格者のインタビューを作成することができました。ありがとう。
Yenching Academyはすばらしいプログラムにも関わらず日本ではまだあまり知られていないので、もっと多くの人に知ってもらいたいなと思っています。そして、弘暉さんが教えてくれた貴重な情報などを参考に、これからも私や弘暉さんに続く人たちが増えていくことを願っています!Yenching Academy、北京、中国、おもしろいですよ!!
ぜひみなさん、頑張ってください!
受かったらインタビューさせてくださいね(笑)
<参考記事>
北京大学Yenching Academyでの経験まとめ:第4期生 曽根理紗

【北京大学大学院燕京学堂 説明会のお知らせ(2022/10/8(土)21:00-22:00)】
(記事のはじまり)
私が中国で所属している北京大学大学院燕京学堂(Yenching Academy: イェンチン・アカデミー)。中国と世界について英語で学ぶことができる全額奨学金の「エリート」修士プログラムとして知られています。中国に興味があったり中国で勉強したい海外の人の間では結構有名で実際に応募もいっぱいある一方、日本ではまだまだ知名度が低いです。そのため、私はこれまでYenching Academyがどんなプログラムなのかとか、その応募方法、自分自身の経験などについて書いてきました。(記事最下部に関連記事あり)
今回は、Yenching Academyでの同級生である曽根理紗にプログラムでの経験などについてかなり詳しくシェアしてもらいました(第4期生の日本人は私と理紗だけでした)。私も1年目の経験については以下の記事でまとめましたが、理紗は1年目だけではなく2年目についても詳しくまとめてくれました。
私は2年目に「ミドルキングダムの冒険(Middle Kingdom Adventure)」というプロジェクトを始めてずっと中国各地を旅していましたが、理紗は国連で働いたり、国際会議に参加したり、研究などをしていました。私たちの経験や活動を見比べてもらうと、プログラム絡みの経験が主な北京での1年目となんでもどこでも自由にできる2年目があるというYenching Academyの特徴がわかってもらえると思います。
ぜひ参考にしてみてください!
私たちはYenching Scholarとしてすばらしい人々に出会いすばらしい経験をしてきたのでYenching Academyはすごくおすすめです!!
(以下の文章はYenching Academy第4期生の曽根理紗が書いたものです)
------------------------------------------
応募しようと思ったきっかけ
日本での学部時代から東アジアの国際関係や日中関係に強い関心があり、イギリス留学やシンクタンクと国際NGOでのインターン、さらに様々な海外プログラムに参加する中で、中国の視点からも同トピックを学びたいと思い、中国へ大学院留学に対してなんとなく関心がありました。ただその際に、自身の中国語のレベルの低さと、中国の大学で外交を学ぶ上での視点の偏りに対する学術面における不安等からやはり厳しいかなと感じていた頃に、当時の私の大学が燕京学堂プログラムの一Cooperative Universityに加盟したというお知らせを学内ポータルサイトで発見し、「これだ!」と見た瞬間に感じ応募することとなりました。
1年目の経験
選択科目で計15単位修めなければいけない中で私は18単位とりました(秋に10単位:春に8単位)。3単位の授業などは3時間ぶっ通しで行われるケースもよくあり、最初は非常に長く感じます。必修科目もいれると割と時間割が埋まる印象です。
Yenchingプログラムの大きな特徴として、フィールドトリップに多く参加できるという点があげられますが、個人的にそれが学期中に忙しいと感じる一番の要因でした。課題量は比較的こなしていける量だと思いますが、週末に立て続けでフィールドトリップやその他イベントの予定等が入ると、格段に忙しくなった印象です。
基本的には参加している授業の一環としてフィールドトリップに参加しますが、私を含め、百賢アジア研究院(Bai Xian Asia Institute)から奨学金をもらっているBai Xian Scholar の特権として、履修していない授業のフィールドトリップに参加できる場合があります。
※Yenching Academyは百賢アジア研究院が支援するパートナー大学のひとつなので、Yenching Scholarの一部は同時にBai Xian Scholarにも選ばれています(私とこのブログを運営しているKazukiはYenching Scholar兼Bai Xian Scholarでした)
2018年秋:授業とフィールドトリップ
選択科目
- Media and International Relations (3単位)
Yenching AcademyのAssociate DeanであるFan Shiming教授が教える近代メディアが外交に及ぼす影響についての授業。メディアと外交に関心がある人にとっては面白い内容だが、国際関係学を学んだことある人にとっては、比較的基礎的で授業の進行スピードもゆっくりな印象。ただFan教授は、日中関係にも非常に関心が高くとても生徒想いで優しい方なので、個人的に色々聞けば丁寧にかつ的確に対応してくれる。
- Chinese Politics and Public Policy (3単位)
近代中国の国内政治の諸問題を包括的に学べる。共産党の仕組み、中国国内の格差問題や、インターネットの検閲等、ありとあらゆる問題について比較的正直に議論される。新疆問題等についてのセンシティブなトピックに関して、たまに教授の変な発言があったりしたが(慣れない英語で話しているのも一要因のように見受けられた)、天安門事件などについても自由に議論できる雰囲気だった。ただ毎週違う問題を扱うため、見方によっては内容が広く浅く、深いところまで議論しきれていないという点は否定できない。
- Venturing into China: Entrepreneurial Innovation in the 21stCentury (2単位)
今、中国で起業する上で必要なことを包括的に学べる授業。実施にグループを組んでビジネスプランをプレゼンしフィードバックをもらう。ただビジネス専攻の人には、比較的内容が基礎的すぎるかもしれない。
▶︎フィールドトリップ1
行き先:北京(深センと並ぶ中国のシリコンバレーと呼ばれる中間村)
時期・期間:11月中旬、日帰り
内容:Microsoftオフィスに訪問。中国マイクロソフトの製品や事業内容についての説明を受けた。

▶︎フィールドトリップ2
行き先:杭州&江南水郷
時期・期間:12月中旬、二泊三日
内容:中国のイノベーションの中心地として注目を集める杭州で、それに関連した多くの施設に訪問。例えば様々なロボット技術を展示した「萧山机器人博展中心(XiaoShan Robot Expo Center)」やイノベーションパーク、第五回World Internet Conferenceが開催された会議会場とその周辺の唐時代の古い建築物が残る水郷など。


- Theory and Practice of Chinese Foreign Policy (2単位)
中国外交にセオリーがあるのかないのか議論を呼ぶなかで、教授はそれがあるとし、近代中国の外交政策についてとても深く切り込んだ内容の授業。学部で国際関係学を専攻した私にとっても非常に満足度が高かった。教授の英語のレベルは非常に高く、生徒の正直な(たまにセンシティブな)質問もいつも快く受け入れ、毎授業で非常にアカデミックで質の高い議論がよくうまれた。一方でほぼ毎週、3〜5つのリーディングの内容まとめと自身の論考を織り込んだレポートを提出しなければいけなかったほか、5000ワードの期末レポート提出など、課題がそれなりにきつかった。
必修科目
- China in Transition 1 (3単位)
- Chinese 1 (2単位)
- Field Study –Xi’an (3単位)
※詳細は省略
その他のフィールドトリップ
- 西安(11月中旬、6泊7日)
秋学期に全ての学生を対象に必修として行われるフィールドトリップ。様々なレクチャーや各種遺跡の訪問、企業などの視察、文化体験などがあった。ちなみに、第5期生の行き先は四川省成都とその周辺だった。
- 広州・深セン(12月初旬、2泊3日)
アフリカ系コミュニティやアフリカ関係のビジネスをしている企業などを訪問した。
2019年春:授業とフィールドトリップ
選択科目
- Retrospect and Prospect of International Development Cooperation in China (3単位)
国連での勤務経験を持つ教授による、中国の国際開発について包括的に学べる。アカデミックな開発学というよりは、教授の経験ストーリを織り込んだ国際開発のリアルな仕組みや実際の現場の様子など比較的実践的な内容であったという印象。国際機関に就く上で重要なキャリアパスの選び方や、面接の受け答え等についての直接的な指導もある。
▶︎フィールドトリップ1
行き先:北京
時期・期間:3月下旬・日帰り
内容:AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)のオフィスに訪問。AIIBのプロジェクト内容等についてのプレゼンを聞く。

▶︎フィールドトリップ2
行き先:上海
時期・期間:5月中旬・1泊2日
内容: BRICS銀行とも称されるNew Development Bank(新開発銀行)オフィスに訪問しVice Presidentを交えた会談に参加。

- The Representation of Reality in Chinese Literature (3単位)
NYUの訪問教授がメインで教鞭をとり、中国の近代文学について学ぶ授業。毎週指定された本を読み、円になって内容を読んだ感想や意見等をシェアする。文学を学んだことがない私にとっては、どう本を読んでどう建設的に意見を述べるのが正解なのが分からず少々難しく感じたが、文学には時代ごとの中国社会の問題や政治に対する不満などが物語に反映されているため、時には議論が「中国の政治が中国社会へ及ぼす影響について」といった内容まで広がることが多々あった。
ただ課題として、毎週何冊もの本を読まなければならず慣れてない人にとっては辛い。またメインの教授はアメリカと中国を行き来しなければならず多忙であるため、彼がいない3分の2の間は、彼の助手たち(博士課程の学生)が授業を担当する。その人たちの授業の内容の面白さや授業に対するやる気にはばらつきがある。
- Archaeology of Cultural Exchanges between China and the West (2単位)
イタリア人の教授が担当する、現在話題のシルクロードについて考古学的に学べる授業。それが歴史において、東と西の文明の交流を助ける上でどう重要な役割を果たしたか、時代ごとの陶器や絹の特徴から考察する。考古学のバックグラウンドがなくても参加できる。
▶︎フィールドトリップ
行き先:敦煌
時期・期間:4月下旬・3泊4日
内容:メインは莫高窟。教授とともにまわり、ひとつひとつ丁寧に説明をうける。他にも昔シルクロードの東と西をつなぐ関所だった陽関やクムタグ砂漠・月牙泉に訪れた。


必修科目
- China in Transition 2 (3単位)
- Topics in China Studies Lecture Series (2単位)
- Chinese 2 (2単位)
※詳細は省略
その他のフィールドトリップ
- 大同(4月中旬、3泊4日)
農村の貧困や開発などについて関連する場所を訪問したり、地元政府の人たちの話を聞いた。他にも中国三大石窟のひとつである「雲崗石窟」や崖に建てられたお寺「懸空寺」なども訪れた。
- 廈門・上海(4月初旬、およそ一週間)
内容:China in Transitionという必修科目の授業の一環。
自分たちでトピックごとにグループを組み、フィールドワークを織り込んだ研究を行う。行き先や期間等も予算内であれば基本的に自由。
私たちのグループは、中国人女子大生の結婚観について研究をすることに。その上で、北京大学の他に上海交通大学や廈門大学の学生にインタビューを行うため、上海とアモイ(廈門)に訪れた。上海を選んだ理由は、1点目に中国最大のお見合い広場がある上海人民公園があるため、そして2点目に女性の結婚年齢が最も遅い地域のうちのひとつであるため。アモイを選んだ理由は、一線都市(First-tier City)である北京と上海と比較して二線都市でも調査を行いたかったため、そしてグループメイトの一人の中国人がアモイ大学出身で比較的キャンパス内での調査が行いやすかったためである。よって滞在期間中は主に、大学のキャンパス内で女子大生たちに声をかけ、結婚観について伺うインタビューを行っていた。
ちなみにKazukiのグループは、中国の国際戦略「一帯一路」に関連して、中国と東南アジアをつなぐ高速鉄道計画の建設地などを雲南省で訪問したらしい。



- 杭州(6月初期、2泊3日)
内容:中国文明について考古学的視点から切り込んだ授業のフィールドトリップ。
杭州にある良渚古城遺跡は中国にある最大規模かつ重要といわれる遺跡のうちのひとつで、出土した文物は新石器時代後期から稲作農耕文化(良渚文化)が存在していたこと、つまり中国文明が5000年以上であるということを考古学的に示すものであるとし話題を呼んだ。
良渚博物院(Liangzhu Museum)のほかに、悪天候や人的被害から保護するために遺跡を年中無休で監視する施設や、実際に発掘が行われている採掘場、採掘したものを研究する施設や、中国茶葉博物館(National Tea Museum)に訪れた。




1年目のその他の経験
Yenching では、頻繁に様々なシーズンごとのイベント(ハロウィーン、クリスマス、感謝祭など)、文化ワークショップ、特別レクチャー、キャリア支援ワークショップ等があります。他には、住む寮のフロアごとに分けられた、クラス(班:ban)ごとのイベント(誕生会や映画鑑賞会など)や日帰り旅行などもあります。週末に開催されるものではたまに日帰りのものもあったりするので、そういったものに積極的に参加し充実した日々を送りました。
例:中国茶を学ぶカルチャーサロン、中国伝統工芸であるしんこ細工(練り粉で作った人形)体験ワークショップ、香山ハイキング、北京郊外の農村への日帰り旅行、中国国家図書館訪問、などなど。






2年目の経験(※夏休み期間を含める)
2年目は1年目の時忙しくてなかなかできなかったことをやるように努めました。積極的に会議やフォーラムに参加したほか、特にかねてからずっとやりたかった中国での業務経験(インターンシップ)を積むことに力を注ぎました。
外資系リサーチ企業(上海)でインターン(6月〜7月)
まず夏休みの始めに上海にプチ移住をし、約8週間という短い期間ではありますが、英国系リサーチ企業ジャパンチームのアナリストインターンとして勤務しました。
上海には何度も訪れたことがあったのですが、中期間滞在し生活してみて、改めてグローバルで中国の流行の最先端である上海の街の魅力を感じました。オフィスでは、外資系の企業ということだけあって、英語はもちろん多数の外国語を操る優秀な中国人スタッフ達と共に働き、非常に刺激を受けました。となりのデスクが韓国チームだっただけあって、本当に常に4カ国語以上の言語が耳に入ってくるような環境でした。
当オフィスの日本人スタッフは私のほかに2人しかいませんでしたが、その方々の経歴をお伺いして、日本人として通常と違ったキャリアパスが選択肢としてあることを知りとても参考になりました。
プライベートの面では、ありがたいことに当企業には特別に家賃・食費を補助して頂いたので、一人で上海の一等地に住み、日々近所のレストランで多国籍な食事を楽しむという贅沢な生活をさせて頂き、上海で外資系企業に勤めるとこういう感じかと身をもって体験できたのは良かったです。他には、一人で上海の滞在先(アパート)を探す際の外国人としての苦悩やその際の家賃の交渉術等も経験できて良かったかなと思います。


日中韓ユースサミット(Trilateral Youth Summit)に参加(7月〜8月)
日本外務省及び日中韓協力事務局主催。2019年度は「社会の活性化(Rejuvenating Society)」がテーマでした。一日本代表参加者として、観光業における3か国協力の可能性について議論し政策提言を行いました。
この年は日本開催(東京、長野)で、主催者側が日本人参加者には国内でかかる交通費しか補助できないという条件でしたが、Yenching Academyが「奨学生の国際的な学術会議やシンポジウムへ参加をサポートする」取り組みの一環として、私の東京—北京間の往復フライト分を負担してくれました。Yenching Academyのこういった金銭面における寛大な支援には非常に感謝しています。
BXAIサマープログラム(8月)
Bai Xian Asia Instituteは全ての奨学生を対象に毎年夏Summer Campを開催しており、京都大学がホスト大学を務めた2019年度の開催地は京都となりました。日中韓を中心としたアジアの優秀な学生たちと3週間弱にわたって様々な活動に参加しました。
国連インターン(北京)(9月〜12月)
夏休み後日本から北京に戻ってすぐ、UNESCAP (United Nations Economic Social Commissions for Asia and Pacific:国連アジア太平洋経済社会委員会)の北京オフィスでインターンとして勤務しました。
学部時代から、大学院に行くなら国際機関で一度インターンをしてみたいと思っていたので、1月頃から夏もしくは秋に勤務スタートを目指して本格的にインターン先を探し出し始めました。当初はアジア圏全域で幅広く探し関心があるポストに幾つか応募したりしたのですが、まず連絡が返ってこず、なかなか上手く行きませんでした。
Yenchingのクラスメートで以前国連でインターンをしたことのある人にアドバイスをお願いしたところ、公式のプラットフォームはほぼ機能しておらずコネがないとなかなか通らないとのことで、彼は関心のあったオフィスに直接メールをしたら連絡が返ってきたと教えてもらいました。その助言を聞いて、関心のあるオフィスのメールアドレスをネット上で何とか探し出し、直接CV(履歴書)とカバーレターを送ったところ、唯一返事をくれたのが私がインターンしたUNESCAP傘下機関である「持続可能な農業機械化センター(Center for Sustainable Agricultural Mechanization、以下CSAM)」の北京本部でした。
UNESCAPは私が最も関心があった組織のうちの一つで、アジア太平洋地域のさらなる発展のために当地域内の社会・経済的交流を促進することを任務として掲げています。CSAMは、そんなUNESCAPの下部組織として2002年に北京にて設立され、中でもアジア太平洋地域のサステーナブルな農業機械化に関する技術協力の促進や文化・経済交流を推進するシステムの整備等を通じて、同地域のさらなる発展及び様々な社会課題(飢餓・貧困・環境・ジェンダー格差問題など)の解決を目指しています。私は個人的に、アジア地域のマルチラテラルな国家間協力に強い関心があったので、この機関はまさにぴったりでした。また中国国内における国連の業務のあり方等にも関心があったので、一石二鳥でした。
私が担当した主な業務内容としては、CSAMが抱える各プロジェクトのロジ関連業務の管理やそれに関連したリサーチ業務でした。そういった業務は東京の政治系シンクタンクでインターンした際に経験済みだったので特に問題はなかったのですが、業務の中で感じたのはやはり「国連」という名前の強みでした。
国連の機関が主催するプロジェクトだからこそ、各メンバー国の政府機関が関わってきますし、会議を計画すれば、それなりの役職に就いた各国の政府の代表が参加します。ありきたりですが、その分やはり一つの項目を決定するのに、各国の要求の中間点を何度も会議を繰り返して模索しなければならないので、プロジェクト進行のスピードが遅いなと感じることは多々ありました。
あとはメンバー国各国の分担金で成り立っているという国際政府機関の特質上、予算等のやりくりの手順が非常に複雑かつ面倒な印象を受けました。(例えばオフィス利用のためのボールペンを数箱購入する際も、それにかかる資金の申請のために、ESCAP本部のバンコクオフィスを通して多くの手続きが必要となります)。
他に中国の国連オフィスならではの経験としては、業務上で中国にあるその他の国連機関の北京オフィスの方々とも交流が度々あったのですが、その中で度々、近年の中国が国連への参画に全力をあげていることを感じました。具体的には例えば、中国人スタッフの数や、中国政府の国連予算の中での分担金の額、中国国連40周年を祝うイベントへのお金のかけ方、中国人学生対象の国連への就職支援のイベントの規模、等々です。
3ヶ月という短い機関で業務内容としてはほぼ単純作業ばかりでしたが、実際に中に入って働いてみないと見えない部分が見えたり、多くの貴重な経験をさせてもらいました。何よりもやってよかったのは、インターン期間の後半に、あるプロジェクトの年一の重要な会議が韓国で開催された際に、飛行機代自腹で同席させて頂いたことです。
インターン中は複数のプロジェクトに関わりましたが、その中でもそのプロジェクトは比較的長期間携わっていたので、ぜひそれが実る瞬間に立ち会いたいと思ったのと、オフィスでの事前準備作業そして事後処理作業だけではプロジェクトの意義などが深く理解しきれない点があると感じたので、上司に相談して一スタッフとして参加させてもらいました。インターンが海外で開催する会議に、自腹で参加したのは前例がないそうです(笑)。結果、現場での各国代表の意見交換の場に立ち会うことができ、こうやって国際システムを作り上げるんだなと、目で見て体感することができたので、非常に良かったです。
こういった貴重な経験ができる国連でのインターンは関心のある人には是非オススメしたいのですが、無給である上に多くの場合でフルタイム勤務を要求されます。学生としては非常に厳しい条件になりますが、それでも私が今回挑戦できたのはやはりYenchingから奨学金として日々の生活費が貰えていたからだというのは間違いありません。
Yenchingの2年生は、授業がないながらも学生として奨学金を貰って中国で生活することができます。それが許される環境は世界でも中々ないと思います。この2年目をどう使うかは本当に学生次第で、自由に様々なことに挑戦できる機会なので、それも視野に入れてYenchingに応募するのもアリだと思います。
他に個人的に北京でインターンをして良かった点は、大学周辺とはまた違った北京の一面を経験できたことです。この国連のオフィスがあったところは、亮马桥(Liang Ma Qiao)といって多くの大使館が集まるエリアなのですが、その周辺はそういった政府系機関や外資企業で働く外国人の方が多くいて、非常に国際的な雰囲気でした。
大使館の方たちがよくお昼を食べるエリアへ行くと、店内の7割以上が外国人ということもよくあり、そんなエリアだからこそ、周辺のレストランは多国籍でかつどれも本格的でした。インターン期間中はそういった場所を散策し、北京大学がある学生の街もしくは中国のシリコンバレーと呼ばれる中関村とは違った雰囲気を知れたのは収穫でした。





2年目のその他の経験
- 週末や休日を利用して定期的に国内旅行
- Bai Xian Scholars向けのイベントやフィールドトリップ(Oxfordの教授が担当する安徽省の水郷エコロジーについてのフィールドワーク、2泊3日)等に参加



- 北京のホテルや大学で開催される特別レクチャーや学術フォーラム等に定期的に参加。(東京北京フォーラム、2019 Women in Leadership Forum、China Coal Consumption Cap and Energy Transition International Workshop 2019など)


まとめ
Yenchingで良かったこと/学んだこと
プログラム内容やYenching在籍中に出来る事としては主に上記のようなものが挙げられますが、その他にも多様なバックグラウンドを持ちそれぞれの分野で活躍する優秀なクラスメート達との日常的な交流が、かけがいのない収穫になったと個人的に感じています。
プログラムの特質上、一緒に過ごす時間が長いので、自然と会話したり一緒にハングアウトしたりする機会が多かったのですが、その際に交わした議論の内容や地域ごとの価値観の違い等を肌身で感じ、多くのことを学びました。ロンドンの大学に一年間留学したことがある私ですが、その時よりも何倍も内容の濃いものとなりました。
そしてこれは不思議に思われるかもしれませんが、過去2年間の私の英語力の伸びはイギリスにいた時より何倍も著しいです。それほど、クラスメート達との交流や自身の意見を発しなければいけないという環境にいたのだと思います。
何よりも、バックグラウンドや専門分野は異なりながらも、それぞれ夢を持ってそれぞれのフィールドで活躍する優秀なクラスメートたちに囲まれる環境にいられたのは本当に恵まれていたなと思います。彼ら彼女たちと一緒にいると、私もまだまだ、もっと頑張らなくてはという気にさせられます。2年目も1年目に負けないぐらい忙しく充実した日々を過ごす事ができましたが、それができたのは同様に常に向上心を持って努力を惜しまないクラスメート達の存在がいたからだと思います。今後おそらく幅広いフィールドで活躍をしていくであろう私のクラスメートたちが、世界各国にいると思うと心強いです。何か困った事あったら助けてもらいたいな〜なんて思ったり(笑)。
Yenching Academyは中国について学際的にとことん学べる修士プログラムであると同時に、重要なネットワーキングの機会でもあります。将来の自分に投資するといった意味でも、非常に適したプログラムだと思います。Yenchingでの経験は私の人生において間違いなく重要なターニングポイントになったと実感しています。是非関心のある方は応募してみてください。
Yenchingや中国留学の問題点
これは客観的に感じたことですが、選ぶ授業によって内容の専門性や求められる学術的な質が低かったりします。それは教授の英語レベルの問題であったり、出される課題の採点基準がいまいち分かりにくかったり(要は採点が甘かったり)、内容自体がつまらなく学生の授業へ参加するやる気が欠けていたり、色々な要因がありますが、本当に授業から多くを学んで研究に活かしたいなどと考えているやる気のある学生からすれば、物足りないと思います。
ただ個人的に思うのは、授業内で教授から学べることは限られているかもしれないけど、自主的に出されるリーディング課題(どの授業もそれなりに出ます)を上手く活用したり、学生達の間で議論を交わしたりすれば、割と得るものもあるのではないかと思います。要は受動的にではなく能動的に学ぼうとすれば、Yenchingはとても優れた環境だと思います。実際私も、クラスメートと交わした議論や誰かが発言した意見の方が印象に残っていることが多いです。
ただ技術面の観点から、Yenchingの学生であることで受けられない北京大学の授業があったり(Yenchingの学生はYenchingが提供する授業と北京大学の他の大学院が提供する一部の授業を受講できる感じです)、修論のアドバイザーとして選択できる教授の専門と自分が研究したい分野が一致しない等の問題があったりするので、特定の分野やトピックの研究を極めたいと考えている学生にとってYenchingは学びづらい環境かもしれません。
他には、中国留学の全般として言えるのが、インターネット利用の制限です。もちろん有料のVPNは購入することになりますが、それでも政治的に敏感な時期等は接続状況が悪かったり、とても遅くなったりします。これは、留学するうちに慣れるのですが、それでもやはり課題の締め切りが近い中で、グーグルに接続できなくなったり、読みたい論文がダウンロードできなくなったりするのは本当に悩みの種でした。
また、何人かのYenchingの学生がぶつかった壁が、念願かなって通ったインターンシップも大学の許可が下りなかったため諦めざるを得なかったというものです。北京大学の留学生として、勤務する上で法律的に大学の許可を貰ってビザを更新する(?)ことが必要とのことらしいです。通常はその手続きを踏めば問題はないのですが、インターン先によってはその許可が下りないということもあるようなのですが、その基準が非常に曖昧で(国際機関は審査が難しいと聞いたことがあります)信頼できないので、多くの学生はそれをせずにインターンをしています。ただ真面目な組織や企業はその手続きをちゃんとすることを求める場合もあるので、その際に大学の許可が下りずできなくなってしまうかもしれないのは残念ですよね。中国で外国人として生活する中で、こういう国や組織の規則等で理不尽な対応をされることが稀にあります。
さらに個人的に、中国で病気や怪我をするのは不安だなというのもあります。私は旅行先での虫刺されが原因で、身体全体に発疹ができて熱まで出たということがあったのですが、その時に大学病院に行った際に大量の使い慣れていない漢方薬をもらい、数日使っても効果が出ず傷が残ってしまったという経験があります。なので、健康面で不安のある人はそれ相応の準備をして留学した方がいいかもしれません。クラスメートの中には、よりしっかりとした医療を受けるために個人で高価な保険を購入し、北京にある外国人向けの病院などに行けるようにしている人もいました。
ほかには、最近は良くなってきましたが、北京では空気汚染がひどい日が未だにあります。合計すると年に大体数週間ほどでしょうか。体質によって出る症状は様々ですが私も含め多くの人は朝から頭痛やひどい倦怠感におそわれます。喘息持ちの方や空気汚染に敏感な体質の方は、場合によってはつらいかもしれません。あるクラスメートは非常に敏感な体質の子で、空気が悪い日はマスクをしても咳が止まらなくなってしまうため、家から一歩も外に出られないらしく、とても生活しづらそうでした。
経歴

曽根理紗(SONE Risa)
- 2020年7月 北京大学Yenching Academy卒業 - 中国学(政治・国際関係学)修士号 -「変容する中国の若者の対日観及びその影響」について論じた修士論文を執筆
- 2019年秋 国連ESCAP北京オフィスにてインターン(3ヶ月)
- 2019年夏 「日中韓ユースサミット」日本代表
- 2019年夏 百賢亜州学院主催「BXAI Summer Program 2019」にアジア未来リーダー育成奨学生として参加
- 2018年6月 国際基督教大学卒業(国際関係学専攻)
- 2017年冬 仏パリのホームレス難民への物資支給ボランティア活動に参加
- 2016-2017 英ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS)へ1年間交換留学
- 2016年夏 国連グローバルコンパクト主催「第八回日中韓ラウンドテーブル」のユース日本代表
- 2016年夏 ICU財団主催グローバルリンクニューヨークプログラム(4週間)に参加
- 2015年夏 香港中文大学サービスラーニングプログラム(4週間)に参加等々
- そのほかにも、国際NGOや政治系シンクタンク、民間リサーチ企業等でプロジェクトマネジメントやリサーチ分野でインターン経験を積む
- 日英中トリリンガル
(https://www.linkedin.com/in/risa-sone-01bbb2143/)
------------------------------------------
<参考記事>
Schwarzman Scholars合格者インタビュー:佐々木彩乃さん 〜彩乃さんや選考について〜

【北京大学大学院燕京学堂 日本向け説明会のお知らせ(2023/9/9(土)21:00-22:00)】
(記事のはじまり)
中国の清華大学大学院にあるSchwarzman Scholars(シュワルツマンスカラーズ)。21世紀の新しい政治経済状況に対応できる次世代のグローバルリーダーの育成を目的として設立された全額奨学金修士プログラムで、毎年世界中から超優秀な学生を北京に集めています。
今回そんなプログラムに、日本人の佐々木彩乃さんが合格しました!すごい!
彩乃さんは2020年9月からSchwarzman Scholarとして北京に留学し、1年間でGlobal Affairsの修士号を取ることになります。
そこで!!この記事では彩乃さんのバックグラウンドやSchwarzman Scholarsの選考などについてインタビューしていきます!まだまだSchwarzman Scholarsに関する日本語情報が少ない中、これから応募を考えている方々の参考になれば良いなと思っています。
ちなみに、私はSchwarzman Scholarsの”ライバルプログラム”とされる北京大学Yenching Academy(イェンチンアカデミー)出身ですが、どちらもすばらしくておすすめしたいプログラムなので、この記事を書いています。あ、あと彩乃とは合格前からの友人です(笑)。
<インタビュー内容>
- 経歴
- 志望理由
- 興味分野/問題意識
- 取り組みたいこと/目標
- 選考スケジュール
- 応募書類と面接の準備
- リーダーシップ経験(Leadership Essay)について
- 推薦状について
- ビデオ(optionalな応募書類)について
- 面接について
- 応募したい人へのアドバイス
------------------------------------------------
1. Kazuki:まず、彩乃さんの経歴を教えてください。
1. 彩乃:私は九州大学法学部の卒業生です。九大在学時には、香港のBai Xian Asia Instituteという財団の奨学生として香港大学社会科学部に1年間留学しました。また、以下のような様々な課外活動に取り組み、九州大学総長賞を受賞しました。ただ、大学までは海外経験がありませんでしたよ!
- 第70回日米学生会議副実行委員長
- JENESYS外務省/韓国外交部 訪韓団にて学生団長
- VIA program (アメリカのNPO)でのインターン
- アメリカ大使館のTOMODACHI MetLife Women’s Leadership Program
- One Young World 2019 in London
- 他にはニューヨークやマカオで開催された国際会議に学生代表で参加したことなど

2. Kazuki:個人的な感想ですが、さすが経歴はすごくSchwarzmanぽいなと感じますね(笑)。アメリカや香港など”西側”での経験、活発な課外活動とすばらしい実績、リーダーシップ経験など、Schwarzman にはそのような学生が多い印象です。
次に、彩乃さんがSchwarzman Scholarsに行きたいと思った理由について教えてください。
2. 彩乃:私がこのように様々なことに取り組んできたのは、海外に将来活躍の場所を求めるのであればまずその勝負する場所と人を知らなくてはいけない、と焦っていた部分があったからです。
でも、その一方将来自分の国に対して何かを還元したいという思いから日本を軸にした国際関係に興味を持ちました。最初に興味を持ったのは日韓関係、そして日米関係。私にとって両国は日本に色んな意味で近い国でした。しかし、両国によく足を運ぶようになる中で、「中国」という国の理解なしに今後の国際社会の理解はないと思うようになり、香港に留学しました。ただ、香港も中国本土とは違うので、今度は内地へ…という思いからシュワルツマンスカラーズに応募しました。
また、現実的なことを付け加えると、全額奨学金付きであることが魅力的でした(これまでの留学は全て奨学金でサポートしてもらってきていました)。通常中国の大学の修士号には高い中国語のレベルが求められますが、シュワルツマンに関しては英語で可能だという点も重要でした。
もちろん、世界中から集まってくる人間が本当に素晴らしい人ばかりなので(多くの人は職務経験もある…尊敬でしかない)彼らから、そして環境から学べることも多いと考えています。
3. Kazuki:「「中国」という国の理解なしに今後の国際社会の理解はない」という点は、私もすごく同感です(Schwarzman Scholarsの創始者・Stephen A. Schwarzmanも同じようなことを言っていますね)。中国を好き嫌いで語る人は多いですが、中国という国のあらゆる側面での影響力を考えると、好き嫌い関係なしに中国に対する理解を深めることはとても重要だと思います。
また、Schwarzman Scholarsに奨学金等のサポートが充実していることや世界中からすばらしい同級生が集まっていることも確かですね。私もSchwarzmanの人たちと多少交流がありますが、すごい人がいっぱいいますね(笑)。
そもそも彩乃さんは、特にどのようなことに興味があり、どのようなことに問題意識を持っているんですか?
3. 彩乃:興味範囲はかなり多岐にわたり自分でも困っていますが、特に東アジアにおける協調をいかに図っていくのかということに関しては興味があります。
また、学問的にというわけではないですが教育やテクノロジーの社会実装にも興味があります。(そういう意味では近未来感がある中国は私にとっては最高の場所です!)
4. Kazuki:東アジアにおける協調を考える上では中国を学ぶことは大事ですね。また、中国ではエドテックがとても発達していて、テクノロジーもおもしろいスタートアップなどがあります。ちなみに、北京大学と清華大学のすぐ近くには、中国ソフトウェアのシリコンバレーと呼ばれる「中関村/Zhongguancun」があります。
彩乃さんはそのような興味を持つ中で、何か目標はありますか?Schwarzman Scholarsの先にどんなことに貢献したり、取り組んでいきたいと思っていますか?
4. 彩乃:東アジアにおける強力な経済/文化面での連携を生み出すことに強い関心があります。現在その第一歩として、かずきさんとも知り合うきっかけになったBai Xian Asia Instituteの仲間、かおりとTHE LEADS ASIAというメディアを立ち上げて東アジアのユースを繋ぐ活動を行っています。
個人的には言語や文化も含め日中韓を受容、理解できる基盤を今後自分の中に構築し、3か国の連携を図る際に橋渡し的役割を担える人間になりたいと考えます。そのためにも、常に謙虚な心と好奇心を持ち、実践の中で学ぶことを続けていきます。
更に、日本国内で言えば進路指導やキャリア教育に対して関心があります。
2つの理由からです。1つ目は日本の社会に蔓延する無力感に対して抵抗したいから(笑)昨年、日本財団が出した統計結果で衝撃的なものがありました。
「日本社会の将来は良くなると思う18歳―10%未満」
えっ!と驚くと同時に「わかる~」という感覚に襲われました(笑)
でも何だか悲しくないですか?日本の未来良くなるって思わないまま、日本に住み続けるのって。ということで、若者がこの社会に対して感じる停滞感や無力感をどう解消しつつ一緒に将来に対して希望を持てる社会づくりをしていくのか、考え始めました。その手段としての教育、です。
2つ目は後悔の再生産をしたくないからです。私自身、東京や大阪という大都市に暮らした経験が無く、どちらかというと田んぼや海、山に囲まれて生きてきました(笑)大学に入るまで自分の将来の選択肢に「海外」は皆無。圧倒的に狭い世界で生きてきました。
だから大学に入ってから色々な苦労をしたわけですが、その過程で「実は高校時代にこんなチャンスがあったんだ」みたいなものに幾度となく遭遇しました。早い段階から広い視野で世界を見る事、それができなくとも「知ってはいる」状況を作っておくことが次の行動に必ず繋がると思います。自分や友人の後悔の再生産をしないで済むように常に次の世代のことを考えていたい。その手段が教育です。
現在MIRACT(ミラクト)という教育NPOを立ち上げ代表を務めています。教育には生涯をかけて向き合いたいです。

Bai Xian Asia Instituteのサマーキャンプで訪れた白川郷
(Kazukiと彩乃は共にBai Xianの奨学生でもあり、そこで知り合った)
5. Kazuki:次に、Schwarzman Scholarsの応募書類や面接について聞いていきます。
まず、応募から合格までの大体のスケジュールを教えてください。
5. 彩乃:出願自体は8月でしたが、一次合否は10月ごろ頂きました。そこから早い人は2週間以内に面接がスタートして、11月上旬で全員面接終了。そこから2週間強くらいで結果が来たと思います。
6. Kazuki:応募書類や面接はどのように準備していましたか?
6. 彩乃:出願書類は取り敢えず6月ごろからダウンロードして眺めていました。何を書こうか考える程度でも毎日眺めていると日常から使える題材が出てきたりするのでおススメです。
面接は、ノートを一冊作って、される可能性がある質問をリストアップして回答作成をしていました(実際書いていたことはそこまで聞かれなかったが)。自分で練習するのと他人に見てもらうのは全然違うので、私は良くして頂いている教授に練習をお付き合いいただきました。また、シュワルツマンスカラーズが公開している動画の中に恐らく面接に関わる物があった気がします。繰り返し見て、イメトレしてました(笑)
7. Kazuki:Schwarzman Scholarsの応募書類の一つ・リーダーシップ経験に関するエッセイ(Leadership Essay) について何かアドバイスがあれば教えてください。
7. 彩乃:世界中から本当にすごいリーダー経験を持った人間たちのエッセイの中に自分のアプリケーションがあることを意識するべきだと思います。約5000のアプリケーションの中で記憶に残る一枚にするためには、やはり「自分にしか書けない」「リーダーシップ経験」というものを熟考するべきです。
人は皆、自分の人生に対してリーダーシップを取る必要があります。よく「リーダー経験が無いからシュワルツマンには応募できない」という相談を受けますが自分に対するリーダー経験がない人はいないと私は思っています。自己マネージメントもチームマネージメントも、基本は同じです。そのことから考えると、「自分にはリーダー経験がない、だから応募できない、エッセイを書けない」というようなことは無いと思います。
シュワルツマンのエッセイに求められているのは輝かしい経験の羅列では無く、どんなに小さなリーダー経験であっても、そこから何を学び、いかに自分の思想まで昇華させられているか、という部分にあるように思えます。
自分にとってのリーダーシップとは何なのか。どのようなリーダー像を理想とし、自分は今何に取り組み実践しているのか。そして自分の描くリーダー像はどのような社会を実現するために必要なのか。しっかりじっくり考える必要があると思います。他の人のエッセイを読むことは大事ですが、型を学ぶ程度にとどめ、その後は自分自身に向き合って書く方が良いかな、と個人的には考えています。
こんなに偉そうに話していますが、私は提出日前日にどうしても自分のエッセイに納得できず、1から全部徹夜で書き直しました。
ですが、それまでの数か月間ずっとエッセイのことを頭のどこかに置きながら暮らしていたので、数時間でバーッとかきあげて、締め切りぎりぎりで提出しました。(後から読み直すと色々ミスがあり相当焦りましたが)
ちなみに、私は経験から学んだ「私にとって理想」のリーダーに不可欠な要素について書きました。
8. Kazuki:推薦状はどのような人にもらいましたか?
8. 彩乃:留学先の香港大学にて受講した中国に関する授業で良くしていただいたアメリカ人の教授、中国の企業の方、自分の大学の指導教員(学部長)に書いてもらいました。色んなバランスはあると思いますが、私も多様性、自分の専門との関わりを考えた結果このようになりました。
9. Kazuki:Schwarzman Scholarsの応募書類に入っているビデオ(optional)について、何かアドバイスがあれば教えてください。
9. 彩乃:応募要項にどんなスカラーを求めているか書かれていますよね。普通に読み飛ばす人もいるかもしれませんが私は一つ一つの言葉を分析して自分なりの意味付けを持ったうえで、そのシュワルツマンスカラーズが求めている人間であるということを証明するチャンスが動画だと思っています。
1分の使い方は自由なので、どうやって、記憶に残るか、そして「この子シュワルツマンに合う!」と思ってもらえるか考えました。ですが、いつも締め切りギリギリな私はシュワルツマンの応募も例外ではなく、結局30分以内に完璧なものを撮らなきゃいけない、という追い込まれた状況で撮影したので、実際共有できるアドバイスはそこまでありません…。
10. Kazuki:Schwarzman Scholarsでは、書類選考を通ると海外の面接会場に直接呼ばれると聞きましたが、面接の実態はどんな感じなんでしょうか?
10. 彩乃:面接は年度によって変わりますがロンドン・ニューヨーク・バンコクで行われます(インターナショナル生の場合)。私はバンコクで受けるべき日程の時にロンドンで、ロンドンの日程の時にマカオで予定があったためにオンラインかニューヨークしか選択肢が無く、ニューヨークを選択しました。交通費、宿泊費、食費、全てシュワルツマンスカラーズが出してくれたので金銭面の心配はいりませんでした。ですが、1次の結果が出ると2週間以内に海外で面接、となるので実際私のようにスケジュール調整が難しい場合もあるようです。
ニューヨークには2泊3日で滞在しました。その中で、面接は半日で終わるので空いた時間に面接会場で知り合った候補者と出かけたり、ニューヨークに住む友人たちと会ったりしました。
11. Kazuki:最後に、これから応募しようと思う人たちへ何かアドバイスをお願いします。
11. 彩乃:実際、振り返ってみると私は3年生の頃から戦略的にシュワルツマンへの出願を考えていました。応募を検討している方の参考になるかもしれないので私が行っていたことを共有させていただきます。
私は、合格者紹介ページがシュワルツマンには存在するので、そのページを読み、どのような人が求められているのか分析したり、私をシュワルツマンが採用するならば140名のスカラーの多様性を考慮する中でどのポジションになり得るか考えました(ダイバーシティの問題で金融に興味ある人ばかり、男性ばかり、アジア人ばかり等は起きえないと分かっていたので)。一旦、自分は「このポジションでスカラーになれそうだ」と見当がつけば、後は自分がそのポジションに最適合することを証明する要素を過去の経験から洗い出す、又は応募までの期間で創り出します。それと同時にエッセイでは自分が設定した「このポジション」がいかにシュワルツマンスカラーズにとって重要であるのか、必要なのかという説得を織り交ぜていく必要があると思います。
------------------------------------------------
今回彩乃さんの協力のおかげで初めてScharzman Scholars日本人合格者のインタビューを作成することができました。ありがとう。
Schwarzman Scholarsはすばらしいプログラムにも関わらず日本ではまだあまり知られていないので、もっと多くの人に知ってもらいたいなと思っています。そして、彩乃さんが教えてくれた貴重な情報をもとに、これから彩乃さんに続く人たちが増えていくことを願っています!!(私が所属する北京大学のYenching Academyにも増えてほしい!!)
ちなみに、彩乃さんが紹介してくれた情報は本当に貴重だし、選考などに関する考え方や取り組み方はとても重要なので本当に参考にしてほしいです。私自身もYenching Academyに応募したときは彩乃さんがアドバイスしたようなことの多くをしていました。
では、興味のある方々はぜひ挑戦してみてください〜!
あ、受かったらインタビューさせてください(笑)
<参考記事>